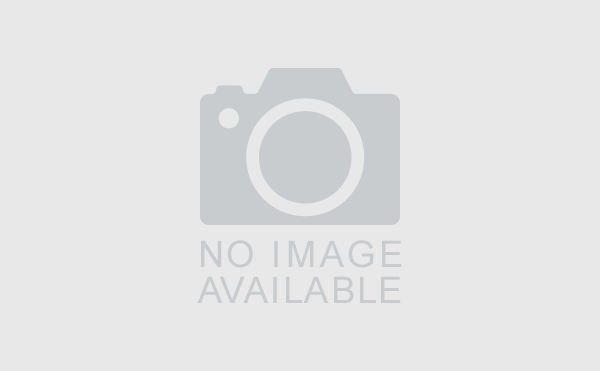宮澤・レーン事件を語り継ぐつどい 戦時下の宗教統制と弾圧
7月12日午前にレーン夫妻の墓前礼拝を終え、同日午後2時から”道内キリスト教会の戦争責任と戦後の歩み”についての集いを札幌北光教会で開催しました。
戦後80年、二度と戦争を起こさせないために戦時下で何が起こったかを忘れてはいけないと、今回は戦時下の教会をテーマに講演会を行いました。
講演1 「戦後80年 戦時下の教会を取材して」
伴野 昭人氏(北海道新聞報道センター編集委員)
講演2 「『世である教会』を目指して― 豊平教会の分かち合い活動と平和」
稲生 義裕氏(日本キリスト教会豊平教会牧師)

<講演1> 道新で日曜日に「私たちの平和論ー2025年戦後80年 戦争の正体を追う」という記事を連載している伴野氏は「戦時下の教会」と題して話しました。
植民地だったパラオなどを取材する中で天皇制について考えるようになり、更に戦争とキリスト教、戦時下の国家とキリスト者との関係に関心を持ち、取材を進めました。
1941年、戦時下で日本基督教団が国によってつくられ、軍用機を国に奉納するなど戦争体制に迎合していく一方、多くのキリスト教会牧師などが投獄され弾圧されました。小樽の内田ヒデ牧師は札幌の拘置所でポーリン・レーンさんとめぐり合い、「神様が遣わした天の使いにめぐりあった」と遺しています。
植民地の朝鮮でも多くの教会が廃止され、多くの信徒が投獄され、犠牲になった事実がありました。
戦時下の教会の実態は資料が少なく明らかになっていませんが、北海道では最近になって遠軽教会で歴史的文書が見つかり、教会が戦争に飲み込まれていく実態が明らかになりました。教会の歴史は日本の歴史の1つとして掘り起こしが必要です。
1967年、日本キリスト教団は戦責告白を出し、戦争の過ちを認め、謝罪と反省の意を表明しました。札幌豊平教会は1996年に戦責告白をし、二度とこのような過ちを犯さないよう教会は何をすべきかを問い、様々な活動をしていると話しました。(このことは講演2で豊平教会の稲生牧師が話されました。)
<講演2> 日本キリスト教会豊平教会牧師の稲生氏です。
最初に北海道、札幌の歴史について。北海道の開拓は先住民であるアイヌの人々の土地を奪う入植植民地政策として進められ、国内貧困対策として北海道・札幌への移民が奨励されましたが、支援金の打ち切りにより札幌の豊平地域は困窮した人々が集まる地域になりました。
その中で「遠友夜学校」が開校され、スミス女学校(今日の北星学園)を開設した宣教師のサラ・スミスさんが日曜学校を開き、この日曜学校が札幌豊平教会の淵源となりました。しかしスミス宣教師は1932年にアメリカ人宣教師の帰国命令により帰国されます。
宗教活動を国家の統制下に置くための手段として宗教団体法が制定され、教会は日本基督教団に集約され、戦争体制下に置かれました。
戦後の豊平教会は終戦50周年に戦争下の教会が犯した過ちを認識するに至り、罪の告白と新たな宣教の決意を表明しました。
二度と過ちを犯さないために教会は何をすべきかを様々な活動を通して考えてきました。平和の問題で重要な課題の一つは貧困問題で、教会では地域の方々の協力を得て地域の子供たちに向けて子ども食堂を始め、現在では多くの子供たち家族が利用しています。
豊平教会が建てられた歴史的意義を振り返り、戦争下の教会を反省し、平和で自由で公平な社会の実現を求めて活動を続けると話されました。



戦時下の教会を語る伴野氏 多くの参加者が熱心に講演を聞く 戦後の豊平教会の活動を熱
く語る稲生牧師